発達障害やグレーゾーンの子供の就学先を選ぶとき、「普通級・支援級・特別支援学校のどれがいいのか」で迷っている方は多いと思います。
私自身もそのひとりでした。
けれど、支援級に通い始めた息子の2ヶ月間を通して、「どこが合っているか」という視点だけでは足りなかったと感じています。
今回はその経験をもとに、就学先を選ぶときに注目してほしい“もうひとつの視点”についてお伝えします。
なお、わが校の話しとなり、すべての学校が同じ対応をしているわけではありません。一部の保護者の意見として参考になれば幸いです。
体験を語る前に|「普通級」「支援級」「特別支援学校」ってどう違う?
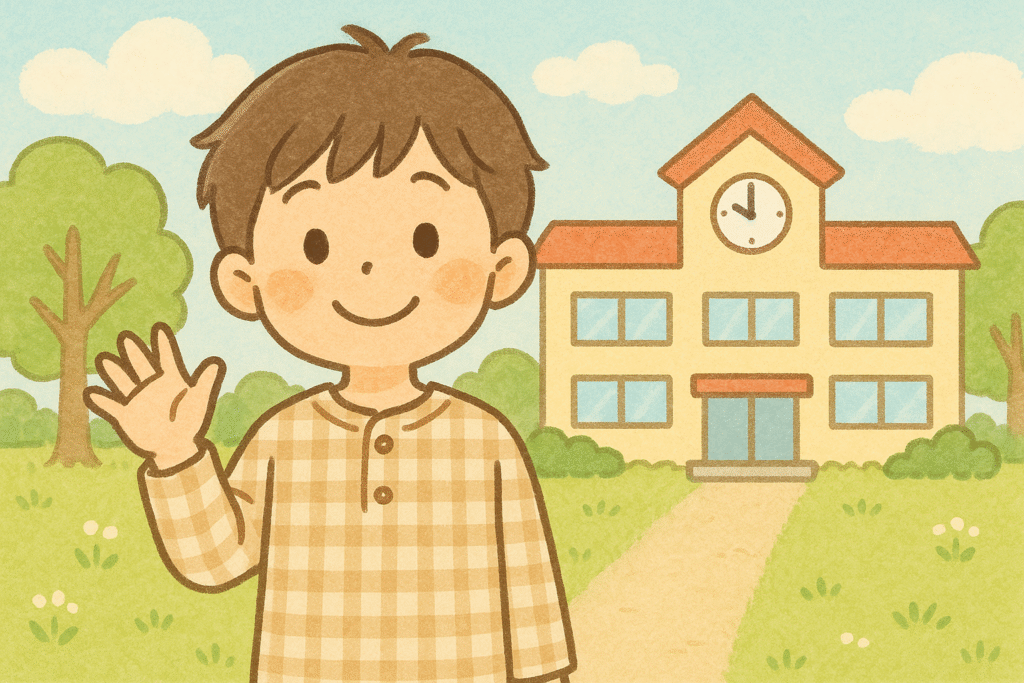
本題に入る前に、就学前の私自身が混乱した「分類の違い」について、ざっくり整理しておきます。
- 普通級:一般的な学級。学力・行動・コミュニケーション面に特段の支援を要しない子供が対象。支援はあっても限定的です。
- 支援級(特別支援学級):通常の学校内にあり、学習面・情緒面で配慮が必要な子が対象。少人数で支援のある環境です。知的障害や自閉症、グレーゾーンの子供など、普通級での生活や授業に不安がある児童が集まる。普通級と併用しながら、特性に合わせた授業スタイルが可能。
- 特別支援学校:より手厚い支援が必要な子供を対象とした学校。教育だけでなく、生活支援や安全面にも特化。中学部や高等部と一緒になっている学校もあり、将来を見据えた活動を積極的に行っている。障がいがある子供が通学可能。グレーゾーンの子供は入学できません。
この3つには明確な線引きがあるわけではなく、お子さんの特性と「地域の受け入れ体制」によって大きく変わることも知っておいてください。
就学相談を経て「支援級」
息子は自閉症と知的障害があり、言語の遅れが著しいです。
会話レベルは「2歳半」とWISC(ウィスク)で結果が出ており、親としては支援級よりも特別支援学校を希望していました。
ですが、就学相談を受けた結果は「支援級」。
「最初は厳しいかもしれないけれど、今後の成長を見込んで」というのが、教育委員会の判断でした。
不安をいだきながらも、「支援級の見守りでも十分にやっていける」と説明をうけ、支援級に入学を決定。
けれど、通い始めてわずか数週間で、思いもよらない出来事が起こります。
普通級で給食を食べていた息子
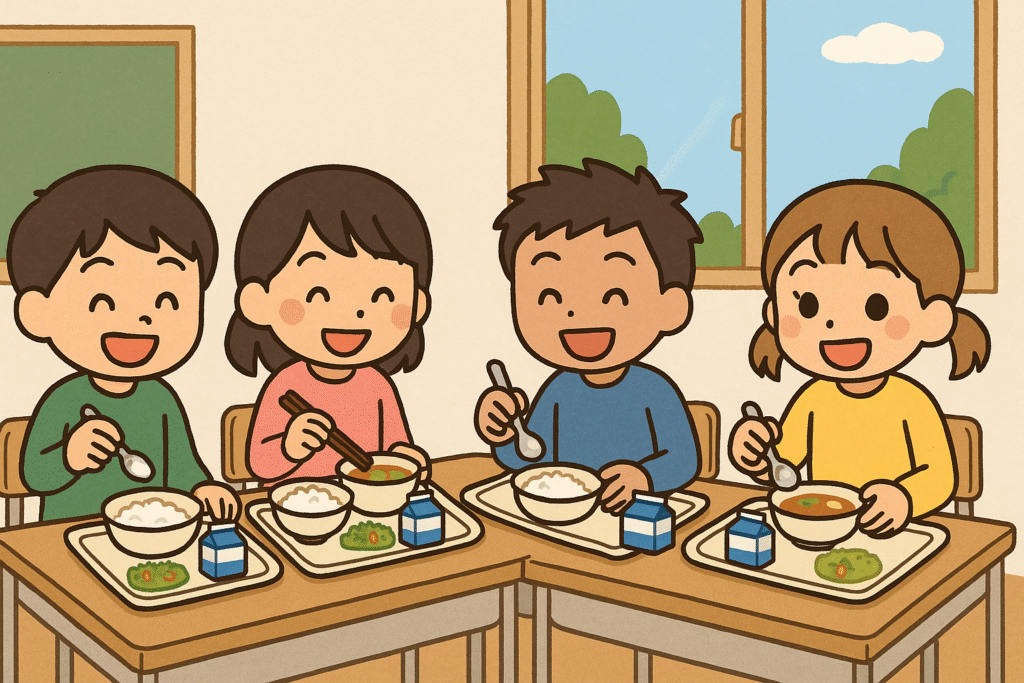
4月中旬、息子と同じ下校班の女の子が話しかけてきました。
「今日、息子くんと一緒に給食食べたよ!」
一瞬、何のことかわかりませんでした。
その子は普通級の児童。支援級の息子と一緒に給食を?不思議に思い、担任に確認したところ…。
「目を離した隙に普通級に入って給食を食べていた」とのこと。しかも、親にはその報告はなし。
「報告するほどのことではないと思いました」と言われたとき、心配より先に怒りが湧きました。
支援級でも「自由時間の見守り」は保証されない
後日、支援級の主任からもはっきりこう言われました。
「また同じことが起きるかもしれません」「付きっきりの対応は難しいので」
もちろん、すべての責任が学校にあるとは思っていません。
ですが、息子の特性を理解していながら、「仕方がない」で済ませようとする対応に疑問を感じました。
実はもっと起きていた“ノーマークの時間”
この給食の件だけではありません。入学からたった2ヶ月の間に、
- 行間休みに戻ってこられず、先生・私で捜索
- 下校時、別の昇降口から出てしまい、すれ違いのまま帰路へ。途中の道路で確保。
- 校内探索の授業中に失踪
など、「ちょっと目を離した」では済まされないことが何度も起きました。
支援級=安全とは限らない!現場は“学力中心”の支援
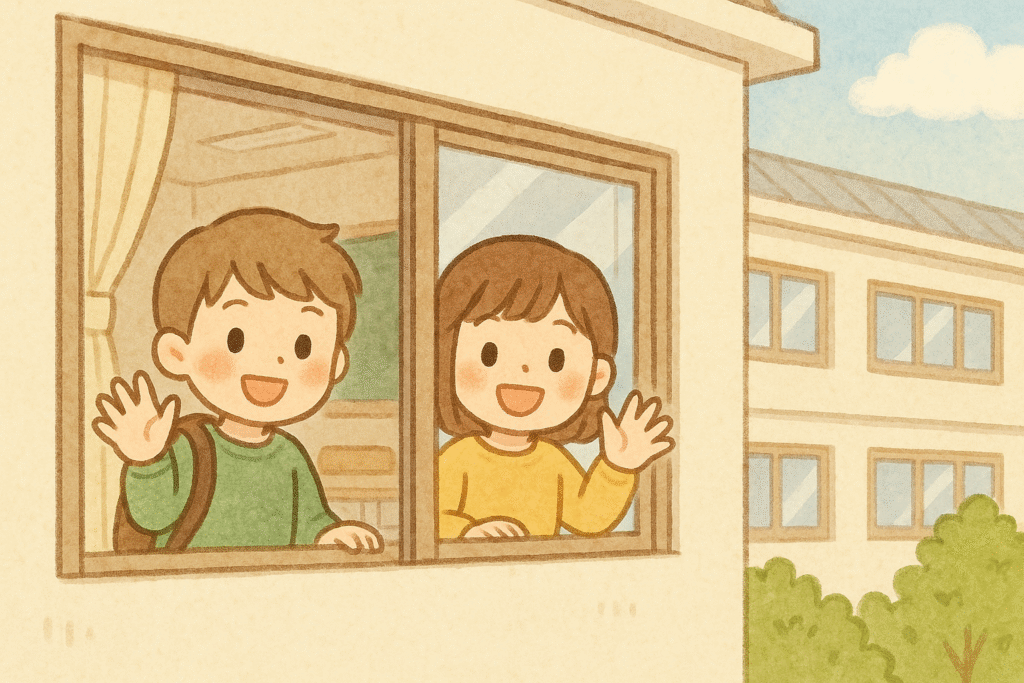
強く感じたのは、支援級が「学力の遅れ」に対応する場として捉えられているということ。
息子のように「次の行動がわからないと混乱する」「誰かにくっついてしまう」タイプの支援は、正直あまり対応できていないように思います。
その大きな理由は「一人に付きっきりは難しい」というもの。
とはいえ「集団行動が難しいから支援級にいるのではないか?」という疑問もあります。
「対応できない」という原因を知りながらも、「職員数に限りがあるため個別の対応は難しい」というのが現実のようです。
「支援級は障がい理解がある」と思っていた私は、支援級の限界を身をもって知ることになります。
自由時間をどう過ごせるか?この視点を忘れないで
就学先を考えるとき、多くの方が「授業についていけるか」「集団に馴染めるか」に目を向けると思います。
けれど、私がいま最も大切だと感じているのは、“授業以外の時間をどう過ごせるか”という視点です。
- 休み時間や掃除時間、見守りはあるか?
- 一人になっても落ち着いて行動できるか?
- 教室を出てしまったとき気づける体制はあるか?
この視点が、子供の学校生活を送るうえでとても重要だと思いました。
現在は「給食後に下校」するスタイルに
息子はいま、給食を食べたら下校するという形をとっています。
理由は、給食後から掃除~昼休みにかけて30分以上「ノーマーク時間」となるからです。
その時間、先生は掃除の巡回や午後の準備で職員室に戻る必要があるため、「常時見守りはできない」とのこと。
そのため、学校と話し合い、安全を考量した結果、給食後の下校となった次第です。
話し合える学校だったから今のかたちがある
わが校は、入学前から支援級の先生と相談の機会を設けてもらっています。
息子の特性や家庭での様子、心配していることを率直に伝えることがきました。
一方で、学校での対応の限界もしっかりと伝えてもらっています。
だからこそ、給食後に下校するという今の形で双方が納得できたのだと思います。
正直、「あまり口を出すとモンペと思われるんじゃないか」と葛藤もありました。
ですが、素直な気持ちを伝えることができたから、今のかたちがあるのだと思います。
学校それぞれで特長も異なります。わが校よりも対応が厚い学校もたくさんあるでしょう。
私の体験もごく一部のものです。
子供を安心して預けられる環境であるのかを見極めるために、就学前から足を運んで「相談に乗ってくれる小学校であるか」を確認してもよいかもしれません。
まとめ|「勉強の遅れ」よりも「安全に過ごせる環境」かどうか
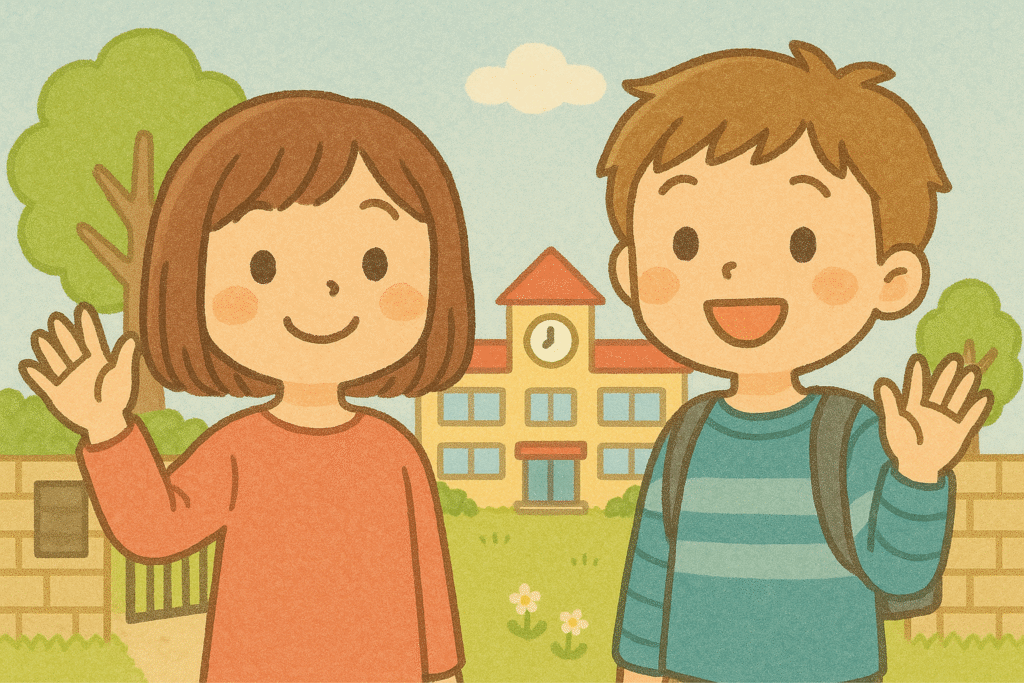
普通級、支援級、特別支援学校。どれを選ぶべきかに正解はありません。
ですが、「どこが合っているか」だけでなく、「どこなら安心して通えるか」という視点も、どうか忘れないでください。
通ってみて合わないと感じたら、転籍という選択肢もあります。
大切なのは「最初の判断を失敗しないこと」ではなく、その時点で“必要な環境”を見極めることです。
自由時間や放課後の動きまで含めて、「この子がここで1人になっても大丈夫か?」という視点から、学校選びをしてみてください。

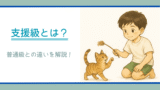
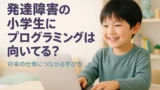
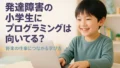
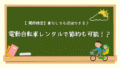
コメント