支援級とは、特別支援学級のことを指し、特別な支援が必要な児童や生徒が通う学級です。通常学級と異なり、個々のニーズに合わせた教育を提供することが特徴です。この記事では、支援級の概要や対象児童、教育課程についてわかりやすく解説します。
支援級とは?

義務教育には、以下の3つの学びの場があります。
- 通常学級
- 特別支援学級(支援級)
- 特別支援学校
この記事では、その中の特別支援学級(支援級)について、その概要や対象児童、教育課程をわかりやすく解説します。
支援級の概要と役割
支援級とは、特別な支援が必要な児童生徒が通う学級です。通常の小中学校内に設置されており、特別支援学級とも呼ばれます。特別支援学校とは異なり、通常学級と交流しながら学べる環境が特徴です。
支援級では、少人数制を活かし、一人ひとりの特性に合わせた学習支援が行われています。学力の向上だけでなく、生活面や社会性を育むためのサポートが含まれているのが特徴です。
たとえば、日常生活のスキルを学ぶ取り組みや、コミュニケーション力を高める活動が取り入れられています。
支援級の役割は、通常学級での学習や生活が難しい子どもが、自分のペースで成長できる場を提供することです。
無理なく学び続けられるよう、基礎学力をつける学習指導と、生活力を身につけるための支援がバランスよく組まれています。子どもが安心して取り組める環境を整え、自己肯定感を育てることも支援級の大切な役割です。
支援級の対象となる児童
支援級の対象となる児童の障害名や特徴を解説。通常級との違いにも触れています。
支援級の対象となる障害
以下のような障害や支援が必要な児童生徒が対象です。
- 知的障害者
- 自閉症者
- 情緒障害者
- 言語障害者
- 弱視者
- 難聴者
- 肢体不自由者
- 病弱・身体虚弱者
支援級に通う子どもの特徴
支援級には、学習面での困難やコミュニケーションの難しさを抱える子どもが多く在籍しており、個別支援計画に基づいて指導が行われます。
支援級の対象となる子どもには、発達障害や知的障害がある場合だけでなく、障害者手帳を持たないグレーゾーンの子どもも含まれます。グレーゾーンとは、診断名がつかないが学習に困難があるケースや、軽度の発達特性がある子どものことです。
特に、手帳がなく特別支援学校に該当しない子どもでも、支援級であれば柔軟な支援が可能です。支援級は、多様なニーズを持つ子どもたちが、それぞれのペースで成長できる環境を提供する役割を担っています。
支援級と通常級の違い
支援級と通常級では、教育方法や学習環境が大きく異なります。支援級では少人数制を活かし、一人ひとりに合わせた個別支援が基本です。授業は個別の課題や支援計画に基づき進められ、子どもの理解度やペースを重視しています。
一方、通常級では集団指導を基本とし、カリキュラムがクラス全体で共通しています。支援級と違って、個別に対応する時間が限られているため、特別な支援が必要な児童生徒には対応が難しいケースが多いです。
また、支援級には支援員や特別支援教育に詳しい教員が配置されていることが多く、子どもたちが安心して学べるようサポート体制が整っています。対して通常級では、学級担任が中心となって学習を進めるため、個別のフォローが難しいことがあります。
このように、支援級は個別支援と生活支援を重視し、通常級は集団活動を通じた学習が主軸となっている点が大きな違いです。
支援級の教育課程

支援級は、通常級とは異なる教育課程を行います。ポイントを抑えておきましょう。
教育内容や指導方法
支援級では、基礎教科(国語、算数など)を中心に、子ども一人ひとりの状況に合わせたカリキュラムが組まれています。通常学級と同じ教科書を使用しながらも、難易度を調整したり、理解を深めるための反復学習を取り入れたりすることが一般的です。
また、学習支援だけでなく、生活スキルを育む学習も重視されています。例えば、身の回りの整理整頓や基本的なマナーを学ぶ時間が設けられており、自己管理力や社会性を高めるための指導が行われています。
コミュニケーションが苦手な子どもには、挨拶や会話の練習といった活動を通して、対人関係スキルを育てる取り組みが実施されています。
指導方法としては、個別支援計画を基にした個別学習や、グループ活動を取り入れた協力学習が特徴です。少人数制を活かし、教員が子どもの特性を把握しながら、きめ細やかなフォローを行っています。
通常学級との連携や交流活動
支援級に在籍している児童も、通常学級の活動に参加する機会が設けられています。代表的な例として、運動会や文化祭、遠足などの学校行事がありますが、これらだけではなく、日常的な授業の一部を共に過ごすこともあります。
たとえば、図工や体育の時間を通常学級と合同で行うことで、他の子どもたちと自然な形で交流できる環境が整えられています。
また、学習発表会や合同学習会を通じて、自分の頑張りを共有する機会も設けられており、お互いの特性を理解するきっかけになっています。
このように、支援級は個別支援と集団活動をバランスよく組み合わせながら、通常学級との交流を大切にする取り組みが行われています。
支援級に通うメリットとデメリット
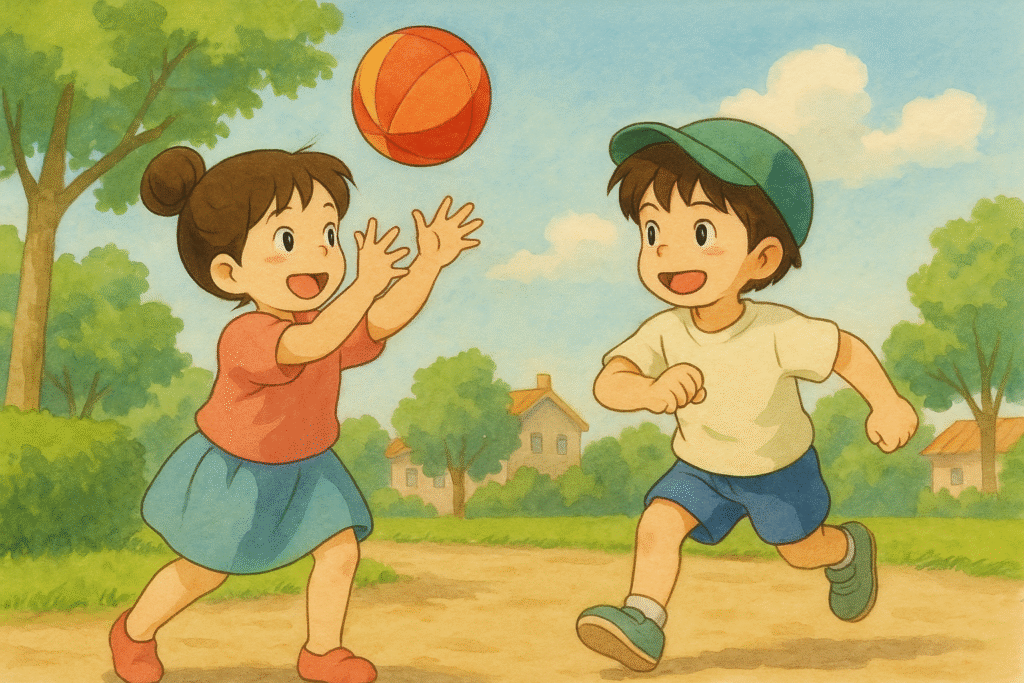
発達に遅れがある児童は、支援級に通うことでさまざまなメリットがあります。一方で、社会性を養う機会が減るなどのデメリットも。詳しく解説していきます。
支援級に通うメリット
支援級に通うメリットは以下の通りです。
1. 個別対応による学習サポート
支援級では、少人数指導を活かし、子どもの理解度やペースに合わせた学習が可能です。個別支援計画に基づき、学習困難がある子どもでも無理なく取り組めるよう工夫されています。
教員や支援員が密接にサポートできるため、安心して学習できる環境が整っています。
2. 生活スキルや社会性の育成
支援級では、学習面だけでなく生活スキルを育む指導も重視されています。例えば、日常生活に必要なコミュニケーションや身の回りの自立に向けた訓練が含まれており、将来的な自立を支える教育が行われています。
支援級に通うデメリット
支援級に通うデメリットは以下の通りです。
1. 社会性の育成機会が限られる
通常学級と比べて、同年代の子どもたちと接する機会が少なく、社会性を培う場が限定されがちです。運動会や学芸会などで交流が図られることもありますが、日常的な接触が少ない点が課題です。
2. 支援内容や学習環境のばらつき
支援級の学習環境は自治体や学校によって異なり、支援内容に差が出る場合があります。特に専門スタッフの配置状況や支援方針の違いが影響し、保護者が環境を見極める必要がある点が難点です。
支援級の選び方と手続き
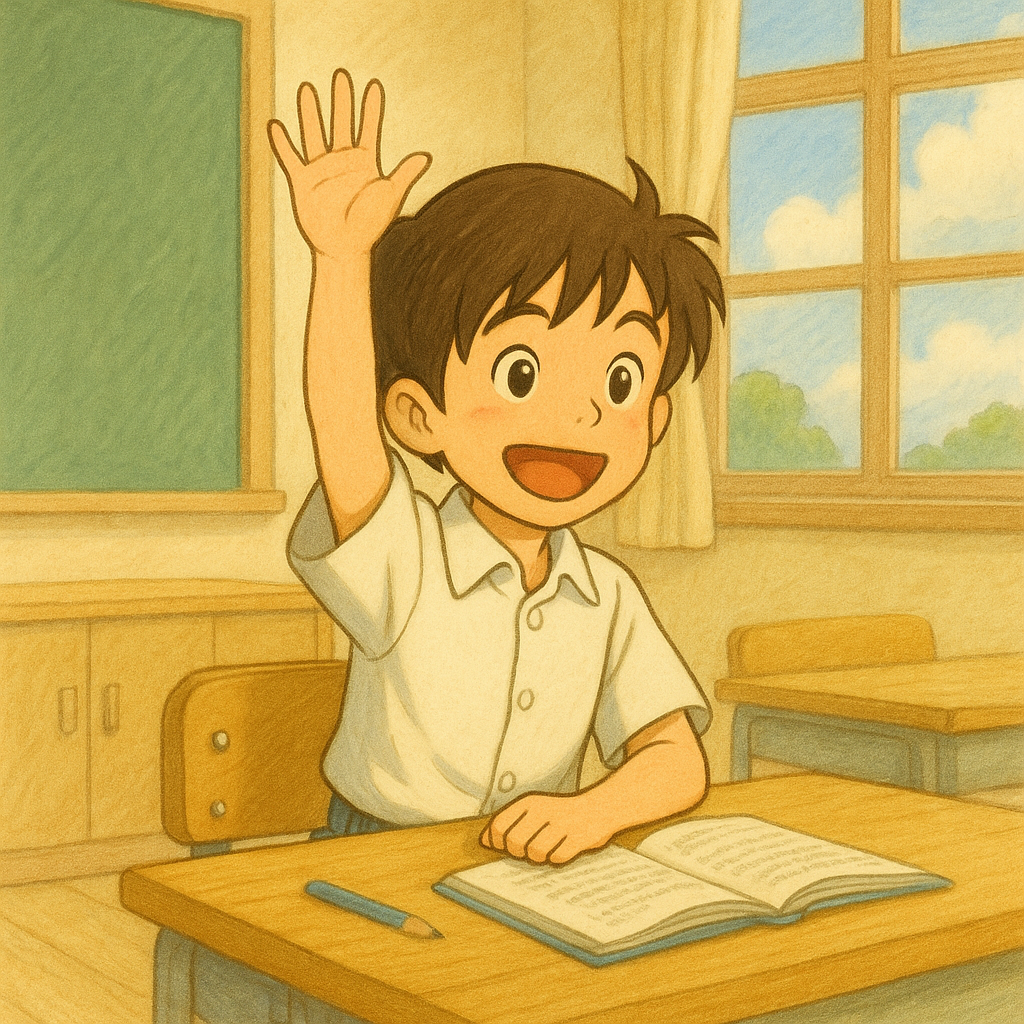
支援級の選び方や手続きは以下の通りです。
支援級選択のポイント
支援級を選択する際には、子どもの特性や支援ニーズを十分に考慮することが重要です。学校見学や教育委員会の相談会などで情報を収集し、実際の支援体制を確認すると良いでしょう。
学校によっては、授業公開日を設けている場合もあります。学校ホームページで公表しているケースが多いので、積極的に参加し、子どもにあった支援であるか見極めることが大切です。
入級手続きの流れ
支援級に入級するためには、教育委員会と相談しながら進めます。専門機関の意見書や医師の診断書が必要なケースもあり、事前に確認しておくことが大切です。
おわりに
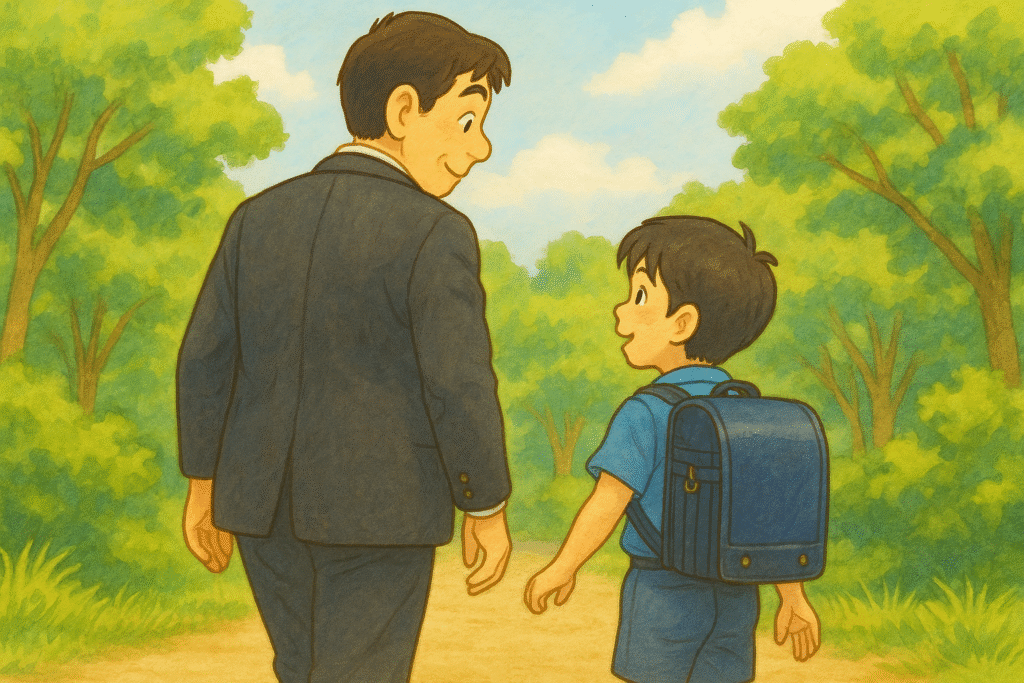
支援級は、特別な支援が必要な子どもにとって、安心して学べる環境を提供する大切な学級です。支援内容が適切であるかを確認し、子どもにとって最善の学びの場を選ぶことが求められています。



コメント